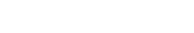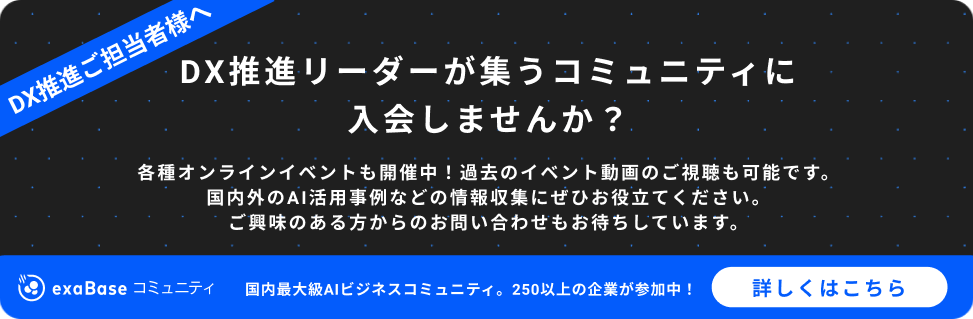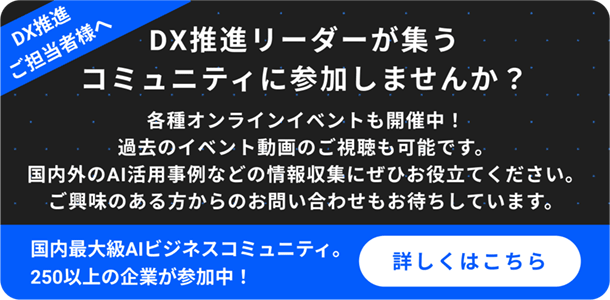AI関連企業に対する投資を見ていると、AIの現状の課題と進化の方向性が見えてくる。これまでは大規模言語モデル(LLM)への投資が集中していたが、最近ではデータ連携やプログラミング支援ツールへの投資が増えているようだ。
まずはAI関連企業は、これまでどの程度の評価額で、どの程度の出資を受けているのかを見てみよう。
この表は米Bay Area Timesがまとめたユニコーン(評価額が10億ドル以上のスタートアップ)のリストだ。

今回のAIブームを牽引するOpenAIが首位なのは納得。2位のxAIは、天才起業家と呼ばれるイーロン・マスク氏の率いるAIスタートアップ。「天才」のすることにはとりあえず出資しておこう、ということなのかもしれない。
CoreWeaveはクラウドサービスの会社だが、それ以外の会社はLLMを開発している。
というように、これまではLLM自体の開発に資金が集中していた。資金を投入すればするほどAIが賢くなるという「スケール則」が機能していたからだ。
しかしいつまでこのスケール則が有効なのだろう?どこまでお金を出せばいいのだろう。
AnthropicのCEOのCario Amodei氏によると、現時点での同社の最先端のAIモデル「Claud 3」の開発には、1億ドルほどかかったという。今開発中の次世代モデルには、その10倍の10億ドルほどかかる見通し。さらに2025年、2026年、2027年には100億ドルから1000億ドルほどの開発費がかかるようになると予測している。
この発言に対し米シリコンバレーの著名投資家Chamath Palihapitiya氏は、「現実問題として、(100億ドルから1000億ドルといった)金額を集めることができるのはMicrosoft、Facebook、Google、Amazon、OpenAIぐらい。この規模の金額になると、出資できるVCもいなくなる。(この傾向が続くと)最終的には1社しか勝ち残らないのでは」と語っている。
勝ち残るのは1社。それではあまりに投資リスクが高過ぎる。
そういう理由からなのか、LLM自体ではなく、周辺のサービスやアプリケーションを開発するスタートアップへの出資が目立ってきた。
1つは、データ連携の分野。企業が自分の持つ社内データを活用することでLLMがさらに賢くなるので、社員の生産性の向上と顧客サービスの改善が見込める。最近では、大量の異なる書類を横断的に検索して質問に答えるツールを開発したHebbia社が、Andersen Horowitzなどの著名VCからの1億ドルの資金調達に成功している。
もう1つは、開発者向け支援ツールの領域。
前回の記事「社員18人、顧客数万社。始まったエージェントAIの時代」で紹介した開発者支援ツールDevinを開発したCognition Labsは、1億7,500万ドルを調達し、企業価値は20億ドルに達した。またロイター通信によると、同じく開発者支援ツールMagicが、前回の資金調達からわずか数ヶ月で、企業価値を15億ドルとする2億ドル以上の資金調達ラウンドに向けた協議を始めているという。またMagicと同様のアプローチをとるパリ拠点のスタートアップPoolside AIは、20億ドルの評価額で4億5000万ドルを調達する協議を進めている。
どんな質問にでも答えてくれる万能LLMが、資金調達競争で勝ち残る1社になるのであれば、差別化は一般企業が自社データとどれだけうまく連携できるかの勝負になるはず。なので今後ますますデータ連携技術のニーズが高まることだろう。
またAIは現在のチャットボット形式から、ユーザーから与えられた目的を達成するために自分で何をすべきか計画して複数のタスクを実行する自立型のエージェントAIへと進化すると言われている。
開発支援ツールのようなエージェントAIへの出資が増えてきているということは、投資家がエージェントAIの未来に期待しているということだろう。今後は開発支援ツール以外にどのようなエージェントAIが登場するのだろうか。注目したい。

湯川鶴章
AI新聞編集長
AI新聞編集長。米カリフォルニア州立大学サンフランシスコ校経済学部卒業。サンフランシスコの地元紙記者を経て、時事通信社米国法人に入社。シリコンバレーの黎明期から米国のハイテク産業を中心に取材を続ける。通算20年間の米国生活を終え2000年5月に帰国。時事通信編集委員を経て2010年独立。2017年12月から現職。主な著書に『人工知能、ロボット、人の心。』(2015年)、『次世代マーケティングプラットフォーム』(2007年)、『ネットは新聞を殺すのか』(2003年)などがある。趣味はヨガと瞑想。妻が美人なのが自慢。