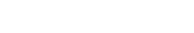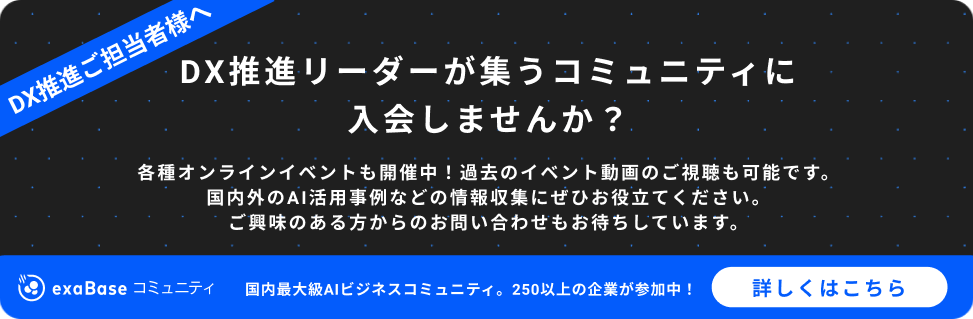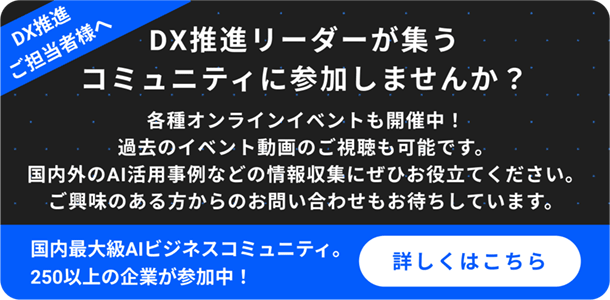AI業界の覇権争いは、AIモデルの性能だけではなく、モデルの性能を引き出すための半導体の性能、半導体をネットワークで繋いだデータセンターの稼働能力に左右されるようになってきた。この覇権争いの中で一番のボトルネックはもはや半導体の供給ではなく、電力の供給になってきている。
AIモデルが巨大化するにつれ、地上でのデータセンター建設は限界を迎えつつある。実際に、AIによる電力消費は2025年末時点でデータセンター全体の約半数を占める勢いで急増しており、各国の電力網(グリッド)はパンク寸前だ。
そんな中、シリコンバレーと宇宙業界の深層で、ある壮大な構想が現実味を帯びて語られ始めている。イーロン・マスク率いるSpaceXが描く「宇宙100GW(ギガワット)計画」だ。
これは、AIの計算資源を、エネルギーの源泉である「宇宙」へ直接打ち上げてしまおうという、コペルニクス的転回である。そして重要なのは、これがもはや「未来の計画」ではないという点だ。
ついにH100が軌道へ:60kgの衛星が実証した「宇宙計算」
「宇宙データセンター」は、もはやSFの絵空事ではない。つい先日、その最初の一歩が静かに、しかし確実に踏み出された。
2025年11月2日、SpaceXのFalcon 9ロケットが「Bandwagon-4」ミッションにおいて、ある特別な小型衛星を軌道に投入することに成功した。宇宙スタートアップ「Starcloud(旧Lumen Orbit)」が開発した、重量わずか60kgの「Starcloud-1」である。
小型冷蔵庫ほどのサイズしかないこの機体の中には、NVIDIAの最新GPU「H100」が搭載されている。
これまで排熱の問題で宇宙での高性能計算は不可能と言われてきたが、彼らは宇宙空間の真空を無限のヒートシンク(吸熱源)として利用する独自の放熱構造と、高効率なソーラーパネルを組み合わせることでこれを克服した。この実証実験の成功は、GoogleやAIインフラ企業Crusoe Energyといった地上のクラウド事業者にとっても単なる静観では済まされない重大なマイルストーンとなっており、実際に彼らも独自の宇宙計画を加速させている。GoogleはProject Suncatcher”を発表。ソーラーパネルを備えたAI衛星のコンステレーション構築を目指しており、2027年初頭までに2機のプロトタイプを打ち上げる計画だ。だ。Crusoe EnergyはStarcloud(旧Lumen Orbit)の衛星に自社のクラウドプラットフォームを展開する計画を持っており、2026年後半の打ち上げを予定している。
Starship × V3衛星:2026年から始まる大量輸送
この成功を受け、イーロン・マスクは次のフェーズへギアを一気に上げた。
Falcon 9による実験が終われば、次は巨大ロケット「Starship」による産業化だ。
SpaceXは2026年から、次世代衛星「Starlink V3」の大量打ち上げを開始する計画を発表している。V3衛星は従来の通信機能に加え、軌道上でのエッジコンピューティング能力が大幅に強化される見込みだ。Starshipを使えば、1回の打ち上げで100トン以上の機材を運べるため、地上への送電ロスなしに、年間100GW規模の計算資源を宇宙へ配備することも夢物語ではなくなる。
宇宙空間には「夜」がない。地上の太陽光発電パネルと比較して、宇宙空間では実に6倍以上の発電効率を24時間安定して得ることができる。地球上で天候に左右されながら発電するよりも、パネルとサーバーを宇宙に浮かべ、そこで発電し、その場で計算してしまった方が、エネルギー効率は圧倒的に高いのだ。
猛追するベゾス:「Project Prometheus」の衝撃
この「宇宙AIインフラ」の覇権争いに、沈黙を守っていた巨人も帰ってきた。
2025年11月18日、ジェフ・ベゾスが新会社「Project Prometheus(プロジェクト・プロメテウス)」の設立を電撃発表したのだ。
創業時の調達額は異例の62億ドル(約9300億円)。OpenAIやGoogle DeepMindから引き抜いた約100名のトップ研究者を擁するこの新会社のミッションは、「物理AI(Physical AI)」の実現である。ベゾスはこれを、Blue Originの宇宙開発ビジョンと連動させ、宇宙空間での自律製造や新素材開発に応用する構えだ。
AIデータセンターを制す者はAIを制す
AIデータセンターを制す者はAIを制す、と言われる中で、AIデータセンターの建設競争は遂に宇宙に飛び出した。
2030年代、私たちが利用する高度なAIサービスの多くは、頭上数百キロの彼方、漆黒の宇宙空間で処理されることになるだろう。AI開発競争と宇宙開発競争が一体化した。われわれは、SF物語が次々と現実になる時代を生きているのだ。

湯川鶴章
AI新聞編集長
AI新聞編集長。米カリフォルニア州立大学サンフランシスコ校経済学部卒業。サンフランシスコの地元紙記者を経て、時事通信社米国法人に入社。シリコンバレーの黎明期から米国のハイテク産業を中心に取材を続ける。通算20年間の米国生活を終え2000年5月に帰国。時事通信編集委員を経て2010年独立。2017年12月から現職。主な著書に『人工知能、ロボット、人の心。』(2015年)、『次世代マーケティングプラットフォーム』(2007年)、『ネットは新聞を殺すのか』(2003年)などがある。趣味はヨガと瞑想。妻が美人なのが自慢。