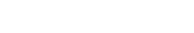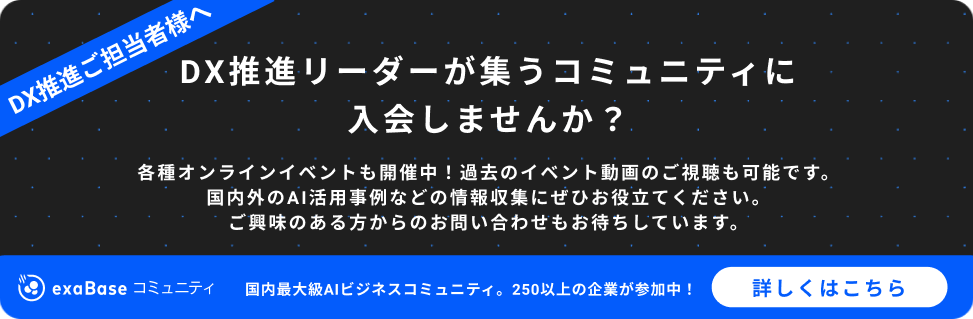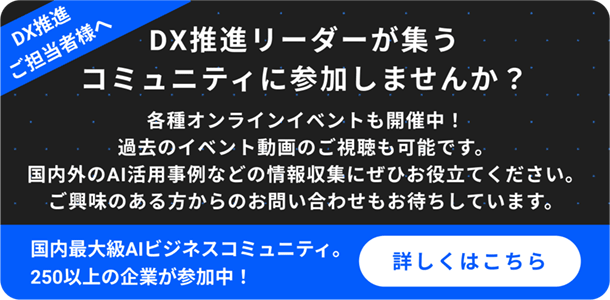再生エネルギーと言えば環境保全を目的に語られることが多いが、AIを進化させるために再生エネルギーが不可欠だという考え方が広がっている。AIを進化させるには大量の半導体が必要で、大量の半導体を動かすには大量の電力が必要。ところが火力発電だけに頼っていれば二酸化炭素排出量が増え炭素税などのコスト増に繋がる恐れがある。一方で再生エネルギーのコストが大きく低下し始めた。AIがわれわれの生活に広く深く浸透する中で、再生エネルギー設備が産業基盤、国家戦略となる可能性が出てきた。
米Googleは、フィンランド南部ハミナのデータセンターに10億ユーロ(約1,600億円)を追加投資すると発表した。理由は簡単。クリーンで安価、そして安定した電力があるからだ。
フィンランドは強く安定した偏西風と低気温が風力発電に向いている国で、夏季は日照時間が長いので太陽光発電にも向いている。また森林国なので林業廃材を使ったバイオマス発電が盛んで、近隣国の水力発電を利用可能な距離にもある。
実際に、フィンランドは風力発電の急成長国だ。2022年だけで新たに2.4GW(前年比+75%)の風力を導入し、総容量は5.68GWにもなっている。風が強い日は電力価格がマイナスになるほどだという。Googleは風力電力を調達することで、データセンターを97%カーボンフリーで稼働させているという。
また寒冷な気候を活かして外気冷却を採用するとともに、データセンターの排熱を近隣の地域暖房網に再利用し、住宅や学校の暖房に活かしている。電力を使えば使うほど街が温まる構造になっている。
再生エネルギーに注目が集まっているのは、AI需要が急速な高まりを見せているからだ。トップAI企業各社はAIデータセンターの構築を急いでいるのだが、1つ問題がある。電力だ。1つのスーパーコンピューターを動かすのに必要な電力は100メガワットと言われる。中規模都市が丸ごと使う電力量だ。OpenAIとソフトバンクなどが進めているStargateプロジェクトなどの大型データセンターには、原子力発電所1基分に匹敵する電力が必要だという。MicrosoftのSatya Nadella氏は「昨年だけで(同社のデータセンターに)2ギガワット(原子力発電所2基分)の電力を追加した」と語っている。
今後もAIデータセンターの建設は急ピッチで行われるとみられるが、そうしたデータセンターの電力を火力発電に頼っていれば、二酸化炭素の排出量が跳ね上がる。そうなれば世論の反発を受けるだけでなく、炭素税負担が膨らむことになる。そこで再生エネルギーが注目され始めたわけだ。米有力誌Forbesは、AI’s Next Great Divide Might Be Clean Energy Access(AIの勝敗を分けるのはクリーンエネルギーかも)という記事の中で、北欧、ブラジル、湾岸地域など、再生可能エネルギーや水力・低電力料金の地域がデータセンターの立地先として有利になってきていると指摘している。記事の中でインフラ企業のMorphware AIのKenso Trabing氏「グリーンエネルギーが余剰となっている地域が、シリコンバレーのような伝統的なテクノロジーセンターを凌駕するようになるだろう」と語っている。
そうした近未来を見込んで、中国ではクリーン電力確保に動き出している。中国の太陽光の発電コストが2020年以降半減しており、風力の発電コストも約 2/3まで低下しているという。対して米国の再生可能エネルギーの発電コストは微減もしくは横ばい程度。さらに2030年までに風力設備は現状比の約2倍、太陽光設備は約3倍、蓄電池は6倍以上、それぞれ設置する計画で、再生エネルギーの発電量が、中国の総発電量の約 40 % を占め、石炭を初めて上回る見通しだという。
インドもクリーン電力戦略を推進している。再生可能エネルギー設置総容量においてインドは 世界4位で、太陽光発電による発電量が108,494 GWh を記録し、日本の 96,459 GWh を上回っている。また太陽光モジュールなどの部品や設備の製造にも力を入れており、輸入依存の低減を図っている。
中国・インド両国とも、AIデータセンターの増設と再エネ政策を一体化させており、エネルギー安全保障と技術競争力を両立させようとしているわけだ。

湯川鶴章
AI新聞編集長
AI新聞編集長。米カリフォルニア州立大学サンフランシスコ校経済学部卒業。サンフランシスコの地元紙記者を経て、時事通信社米国法人に入社。シリコンバレーの黎明期から米国のハイテク産業を中心に取材を続ける。通算20年間の米国生活を終え2000年5月に帰国。時事通信編集委員を経て2010年独立。2017年12月から現職。主な著書に『人工知能、ロボット、人の心。』(2015年)、『次世代マーケティングプラットフォーム』(2007年)、『ネットは新聞を殺すのか』(2003年)などがある。趣味はヨガと瞑想。妻が美人なのが自慢。