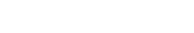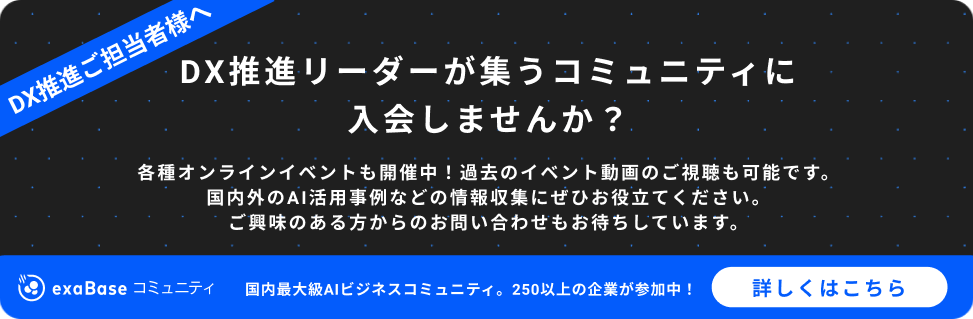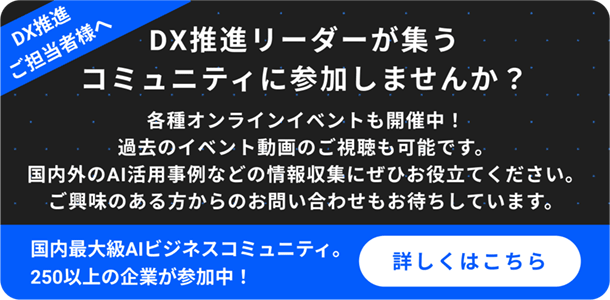生成AIブームが始まって2年余り。多くの企業がAIを使った新サービスを立ち上げたが、その多くは話題にはなったものの、すぐに後発に抜かれているという現象が起こっている。
これまでのITプロダクトは、先に市場に出すことが重要だった。先に市場に出してユーザーを囲い込むことで、競合に打ち勝てた。しかしAI時代になると、スピードだけでは不十分だ。後発が追いつけないような模倣耐性、差別化力がなければ生き残れない。なぜなら後発は、最新モデルを投入するだけで、簡単に追いつけるからだ。そこで必要なのが時間とともに強くなる仕組みだ。
では、具体的にどうすればAIプロダクトを定番化できるのか。米国のプロダクトデザイナーやVCの間で広まっているフレームワークがある。
それが「7-step playbook to build AI products that stick」――成功するAIプロダクトを構築するための7つのプレイブックだ。
ここでは、その骨子を参考に、日本企業としての戦い方を考えてみたい。
1. 戦う領域を明確にする
AIは万能のように見えるが、実際は「どの戦場で勝負するか」を定めなければ勝てない。
「営業支援AI」「教育AI」「医療AI」――どれも広すぎる。たとえば「中小企業のインサイドセールスを自動化するAI」や「英語スピーキング試験の発音だけを矯正するAI」など、特定の痛みに焦点を絞ることが第一歩となる。
領域を決める上で、次の3項目を考慮するのがいいと思う。
(1)高頻度のペインポイント
毎日、または週次で発生する「面倒・時間・コスト」問題をターゲットとすべきだ。一年に1回困る課題より、毎朝30分無駄になる課題のほうがユーザーの注意を引く。「今日は AI があれば楽になる」は、日常体験に埋め込まれやすい。
(2)自然発生データの利用
問題を解決していく過程で、構造化可能なデータが生成されるか。ユーザーの入力、操作ログ、訂正履歴などを使って、後続の予測精度を上げる素材となるデータを自動生成できるかを重視すべきだ。
このデータが「無料で集まる」なら、スケールに伴ってコストではなく資産になる。
(3)隣接化可能性(Adjacency potential)
あなたの最初の領域は「上陸地点」であり、そこから隣接のワークフローに展開できるかどうか。
最初は狭くてよいが、その後「関連領域拡大」が現実的でなければ、成長が止まる。
2. 「AIのループ」ではなく「ユーザーのループ」を設計する
多くの開発チームは、プロンプト → 推論 → 評価という「AI ループ」に注力しがちだ。しかしユーザーはその内部を見ない。彼らが関心を持つのは、結果として日常がどう変わるかだ。
- AIループは差別化要因になりにくい。なぜなら、後発企業が同じモデルや手法を導入できてしまうからだ。一方、ユーザーループは一度組み込まれると強い慣性を持つ。
防御性の鍵は、「ユーザーループ 」を設計することにある。
ユーザーループの典型的な流れは次のようになる。:
- ペイン(課題の発生)
ユーザーは日常の中で繰り返しの摩擦を感じる。 - リリーフ(解放感)
あなたのプロダクトが、その摩擦を速く、簡単に、精度高く処理する。 - 行動変化
ユーザーは、自ら新しいプロセスを「慣れたやり方」代替に切り替える。 - 習慣化
ループが繰り返されることで習慣になる。 - スイッチングコスト
データ、統合、信頼が蓄積することで、他プロダクトへ移る心理的・技術的障壁が高まる。
優れたユーザーループの原則としては、驚き」ではなく「解放」を起点とすること。インパクトのある体験は目を引くが、それだけでは長続きしない。「30分かかっていた作業を 5 分にできる」ような明瞭な効果を起点に設計すべきだ。
また効果を可視化することも大事だ。人は痛みを忘れる。だから「今週これだけ節約できた」など、節約時間や成果を見える化してリマインドする必要がある
フィードバックサイクルを締めることも重要。行動 → 結果までの時間を短くするほど、習慣化は早まる。毎日ループできる構造を優先すべきだ。
意外に見落としがちなのが、ユーザーの感情だ。人は結果だけでなく、「自分が賢くなった」「仕事をコントロールできている」と感じたい。それを体験させる UI や文言を設計に含めることが重要だという。
AIの精度を上げることよりも、まず「毎日使う理由」を生むこと。そこからプロダクトの成長が始まる。
3. 早い段階で「堀(Moat、競争優位性)」を築く
AI の世界で、後からモートを作るという発想は危険だ。ほとんどの場合、後付けでは間に合わない。だからこそ、プロダクト設計の初期段階から モートとなる要素 を織り込むべきだという。
有効なモートとしては、次のようなものが挙げられる。
- データ資産:ユーザー操作・訂正・修正ログ・行動履歴など、他社が持ち得ないデータ
- ワークフロー統合:主要業務フローの中に AI が入り込むことで「横づけアプリ」には戻れなくなる
- 信頼 & ガバナンス:規制産業でのコンプライアンス体制、説明責任、モデル監査性
- 反復速度:ユーザーのフィードバックを迅速に取り込み、モデル改善を短期間で回せる体制
これらは機能ではなく構造要素であり、他社が短期間で模倣できない強さを持つのだという。
4. 機能ではなく「コストカーブ」で設計する
AI プロダクトにおいて、新機能を追加するだけではスケールできない。
重要なのは、時間とともにコストが下がる構造 を設計することだ。
推論コスト(GPU・API使用料)が膨らむモデルを使い続けると、収益性は綻び始める。
初期段階では高性能モデルを部分的に使い、全体には軽量モデルを組み合わせる ハイブリッド構成 を検討すべきだ。
また人手による訂正・ラベル付け作業を、AI とユーザー行動データで自動生成・補正できるよう進化させる仕組みを織り込みたい。
こうした設計を最初に組み込むとで、機能勝負からコスト構造勝負のフェーズに移行できるのだという。
5. 「アドプション・ウェッジ(採用のくさび)」を打ち込む
すべてのユーザーがAIを歓迎するわけではない。
だからこそ、最初に刺さる一点突破の体験をつくることが重要だ。
Canvaが「1クリックで背景を削除」という単機能からスタートしたように、
「これだけは手放せない」と思わせる機能をまず届ける。
初期ユーザーの成功体験が口コミとなり、徐々に市場を押し広げる。それと同時に、隣接ワークフローを徐々に追加していく、ということが大事だという。
6. AIのぐるぐるモデルを回す
AIプロダクトの成長エンジンは、ユーザーからのフィードバックだ。
行動ログや評価データをAIの改善に循環させる「Feedback Flywheel(AIぐるぐるモデル)」を設計することで、プロダクトは自己進化していく。
ユーザー行動 → AI出力 → 修正・評価 → 再学習 → 改善された出力。
このループを高速で回せるプロダクトこそが、「使うほど賢くなるAI」になる。
ポイントは①フィードバックを得やすい UI/UX を備える②モデル改善パイプラインをエンジニアリングで自動化③モニタリングと異常検知の仕組みを設けて、学習偏りやバイアスを早期に検知④フィードバックの質を担保するためのガバナンス設計、ということらしい。
7. 「ヒーロー依存」ではなく「システム」でスケールする
最後の落とし穴は、優秀な人材に頼りすぎることだ。
AI時代の成長は、個人の努力ではなくシステム設計にかかっている。
スケールする組織とは、
-
明確なプロセス
-
自動化されたツール群
-
標準化されたデータパイプライン
-
モジュール化されたアーキテクチャ
によって動いている。
「人が頑張る」のではなく、「仕組みが回る」構造をつくること。
それが、AI時代の組織運営の本質である。

湯川鶴章
AI新聞編集長
AI新聞編集長。米カリフォルニア州立大学サンフランシスコ校経済学部卒業。サンフランシスコの地元紙記者を経て、時事通信社米国法人に入社。シリコンバレーの黎明期から米国のハイテク産業を中心に取材を続ける。通算20年間の米国生活を終え2000年5月に帰国。時事通信編集委員を経て2010年独立。2017年12月から現職。主な著書に『人工知能、ロボット、人の心。』(2015年)、『次世代マーケティングプラットフォーム』(2007年)、『ネットは新聞を殺すのか』(2003年)などがある。趣味はヨガと瞑想。妻が美人なのが自慢。