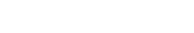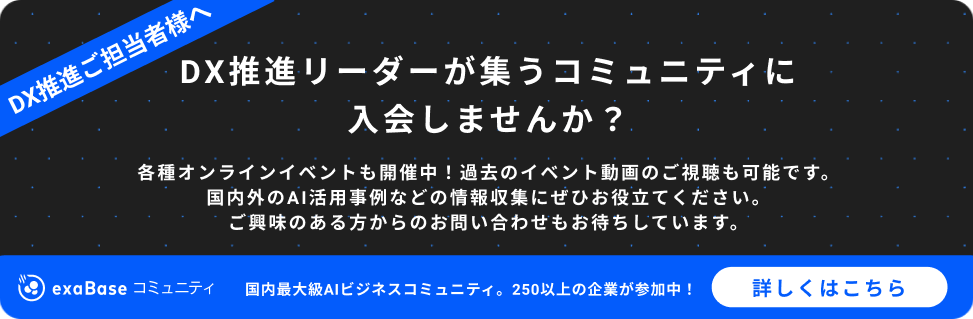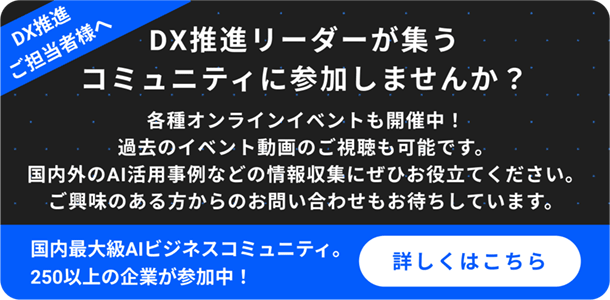半導体大手NVIDIAがここ数ヶ月間に、次々と巨額投資を決めている。データセンター新興企業への出資、クラウド事業者との複雑な契約、さらにはライバルであるインテルへの巨額投資まで。極めつけは、OpenAIに対する最大1,000億ドル(約15兆円)規模の投資計画だ。なぜこれほどまでに巨額の資金を投じ続けるのだろうか。
9/22付のロイター通信によると、NVIDIAはOpenAIに段階的に最大1000億ドル出資し、10GW規模のNVIDIAシステムを段階配備する契約を結んだという。
またクラウド事業者のCoreWeaveが売り切れなかったGPUキャパシティを2032年4月13日までNVIDIAが買い取る契約を結んだ。表面金額は約63億ドルになるという。
このほかAI研究者に特化した中堅GPUクラウド事業者Lambda Labsと約15億ドル規模の契約を提携。LambdaがNVIDIAのGPUを購入し、NVIDIAがそのGPUを借り戻す形でのリース契約になっている。
また英AIインフラ企業Nscale Global Holdingsに対し最大5億ドルを出資すると報道されている。
競合半導体メーカーのIntelに対しても普通株を取得する形で50億ドルを出資するとともに、新しい半導体を共同開発する提携を9/16に発表した。
NVIDIAの投資は、単なる金融的リターンを狙ったものではなく、むしろ影響力を獲得する政治的・地政学的な動きだと見るのが妥当だと思う。主要国に拠点を設けようとしているOpenAIや、英国のデータセンター企業へ出資することにより、NVIDIA自身も各国の首脳とのパイプができることになる。かつて英政府がNVIDIAによるArm買収を阻止した際のような規制の動きを和らげるための外交カードにもなり得るわけだ。
また、NVIDIAが新興クラウド事業者に先行投資し自ら顧客になることで、その企業はGPUを大量購入できるようになる。つまり、NVIDIAの資金は市場に循環し、結局は同社のGPU販売を加速させるブーメラン効果を生むわけだ。
AIデータセンターの建設には数十兆円単位の資金が必要。従来の金融機関が躊躇する規模のプロジェクトでも、NVIDIAが保証人として立つことで資金調達が現実化する。ある意味、同社はAI経済圏の「中央銀行」のような存在になりつつあると言えそうだ。
この構造は、AIエコシステムをNVIDIA依存に深く絡め取る仕組みでもある。クラウド大手のAmazonやGoogleが自社チップ開発を進めているとはいえ、現時点ではNVIDIAのGPUなしには生き残れないのが実情。この機に影響力を一気に拡大しておきたいのだろう。
軍資金はたっぷりある。The Informationの報道によると、NVIDIAの自由現金流(本業で稼いだキャッシュから設備投資などの必要支出を引いた自由に使える資金)は2024年度の269億ドルから、2027年度には1,480億ドル(約22兆円)になる見通しだという。
1480億ドルという数字は世界企業の中でもトップクラスで、日本の防衛費の3倍近い額をNVIDIAは1年で自由に使えることになる。
ただこうした投資は、AI経済が今後も急成長を続けるというシナリオの下で成立する話。もしAI需要が思ったほど拡大しなければ、投資の反動は大きく、収益を圧迫しかねない。
驚くほどの大勝負。果たして吉と出るか凶と出るか。

湯川鶴章
AI新聞編集長
AI新聞編集長。米カリフォルニア州立大学サンフランシスコ校経済学部卒業。サンフランシスコの地元紙記者を経て、時事通信社米国法人に入社。シリコンバレーの黎明期から米国のハイテク産業を中心に取材を続ける。通算20年間の米国生活を終え2000年5月に帰国。時事通信編集委員を経て2010年独立。2017年12月から現職。主な著書に『人工知能、ロボット、人の心。』(2015年)、『次世代マーケティングプラットフォーム』(2007年)、『ネットは新聞を殺すのか』(2003年)などがある。趣味はヨガと瞑想。妻が美人なのが自慢。