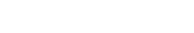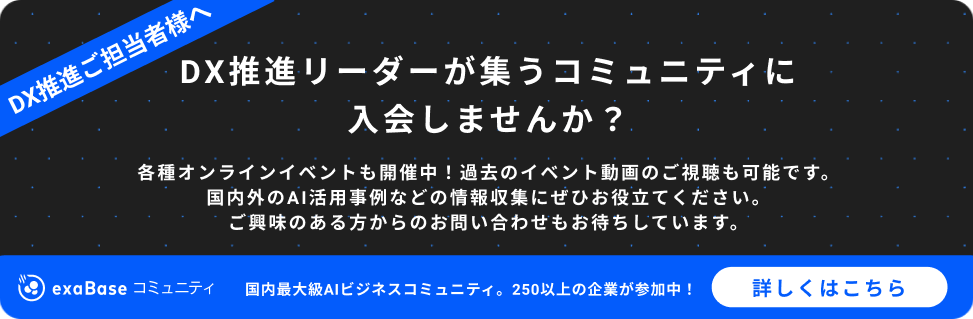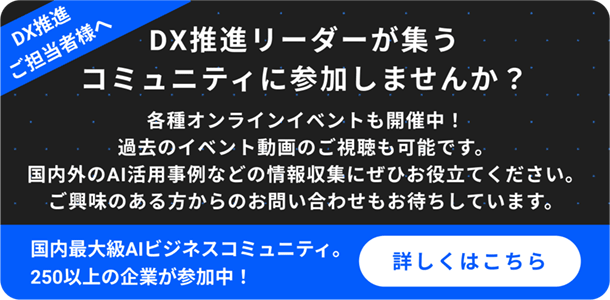【注意】ここで言う「GPT-5」とは、GPT-4の次のパラダイムという意味です。GPT-5という名称のAIモデルが今後リリースされないと主張しているわけではありません。
社会を驚かせないというOpenAIのSam Altman氏のマーケティング施策のおかげで、AIが新しいパラダイムに突入したことに気づいている人はまだそう多くない。しかし米国の一部技術者たちはこの変化にさすがに気づき始めたようで、新しいパラダイムの特徴に関する議論が始まっている。その特徴の1つは、論理的思考のプロセスでぐるぐるモデルが回り、AIの地頭がどんどんよくなる可能性があるということだ。もう一つの特徴は、半導体を買い増せばAIが賢くなるというスケール則が、学習プロセスだけではなく推論プロセスにも有効だということだ。こうした特徴を受けてAIは幻滅期に入るどころか、今後加速度を増して進化しそうだ。
▼Sam Altmanという天才マーケター
OpenAIの次の大型バージョンアップはいつなのか。GPT-4がリリースされてから1年半近く、テック業界はこの話題で持ちきりだった。その大型バージョンアップが、今回OpenAIがリリースした新モデルOpenAI o1であることに、多くの人はまだ気づいていない。なぜなら稀代のマーケターでもあるSam Altman氏の絶妙なマーケティング施策で、社会を驚かさないように細心の注意が払われているからだ。「社会にはAIの進化について考えて適応する時間が必要。われわれのゴールは最新モデルの発表で社会を驚かせることではない。その逆で、驚かさないことだ」。3月19日にリリースされたLex Friedman氏のポッドキャストで、Altman氏はそう語っている。
AIの進化は社会を豊かにする。しかしその進化があまりに急であれば、人々は恐怖を感じ、反発する。Altman氏自身、その反発を身を持って体験している。
新しくリリースされた「o1」に関する技術的なブレークスルーがあったのは2023年10月ごろだと思われる。そのころのインタビューで同氏は「大きなブレークスルーがあった」と語っている。そして11月17日に米サンフランシスコで開催されたAPEC(アジア太平洋経済協力)のパネル討論会に登壇した同氏は、司会者の「2024年に起こるサプライズは?」という質問に対して「(2024年に)AIモデルは、誰も予測しなかったレベルにまで大きくジャンプして進化する」と語っている。
そのパネル討論会の直後、非営利団体OpenAIの理事会がAltman氏に解雇を言い渡した。OpenAIは、営利組織の株式会社OpenAIの上部組織として非営利団体OpenAIが存在するという、変わった組織形態になっている。非営利団体OpenAIの目的は、株式会社OpenAIの作るAIが人類に危害を与えるものにならないように監視することだ。
突然の解雇通告に、当人はもとより同社の従業員や株主も驚いた。95%の従業員が同氏のCEO復帰を求める書簡に署名。Altman氏の復帰がなければ転職する決意を表明した。また株主からの強い働きかけもあって、結局5日後の11月22日にAltman氏がCEOに復帰。非営利団体の理事会は解散となった。
解雇通告の理由はいまだに正式には明らかになっていないが、その後の報道を見ると、論理的思考を持つ次期モデルが人類に危害を与える可能性があると理事会が判断した、というシナリオが最も有力な説と言えそうだ。
AIが論理的思考を持つようになると、どのような危害が人類に及ぶのだろう。この問題に関し、Altman氏自身がWall Street Journalのインタビューに、次のように答えている。「怖いのは、AIによる一人一人に対する説得行為だ。明らかに分かるような形で説得してくるのではなく、知らない間に納得させられてしまっているような働きかけがAIには可能。それが大きな問題になるのではないかと思う」。このインタビューの動画がリリースされたのが2023年10月21日。「大きなブレークスルーがあった」と同氏が語った直後だ。このブレークスルーを受けてOpenAI社内で、いろいろな議論が交わされていたのだろう。
それでもAIは人類にとって大きなメリットとなる。そこでAltman氏は、社会が驚いて反発しないような形での次世代モデルのリリースを考えたのだと思う。前出のLex Fridman氏とのインタビューの中で、Frieman氏が「GPT-5はどんなモデルになるのか。いつ出るのか?」と何度も執拗に聞いてくるので、「世間がそこまで次のモデルに関心があるのなら、大きなバージョンアップではなく、小さな進化があるごとに新しいモデルとして小出しにしていかないといけないのかも」と語っている。
事実その直後からOpenAIは、小さな進化ごとに新しいモデルとして小出しにする戦略に切り替えている。GPT-4oを5月に、GPT-4o miniを7月にリリースしている。そして今回リリースしたOpenAI o1はプレビュー版。これからo1シリーズとして、次々モデルを小出しでリリースしていくことを明らかにしている。
モデルを小出しにするというのが、社会を驚かさない1つの施策だが、そのほかにもAltman氏はいろいろな施策を打ってきた。例えば、モデルの名称を変えてきたこともその施策の1つだろう。GPT-5の登場を待っていたマスメディアは、これが次の大きなバージョンアップなのか判断がつかず、大きく取り上げることができなかった。
またプレビュー版の機能をわざと限定してきた。プレビュー版には、ブラウザ、マルチモーダル機能などが未搭載。その論理的思考に博士号取得者レベルのユーザーが大絶賛する一方で、機能的には前のモデルと大差ないと一般ユーザーからは酷評されている。
さらにはOpenAIのCTOのMiraMurati氏は、Wired誌のインタビューを受けて、GPTシリーズを今後もリリースすることを明言。o1シリーズを傍流の進化だというイメージを打ち出してきた。
こうした施策が功を奏して、今のところo1がGPT-5と呼ばれていた次の大型進化であることに気づいている一般ユーザーはまだそう多くない。
▼新しいパラダイムの2つの特徴
ただ英語圏の著名技術者たちの間では、o1が大型進化であることにさすがに気づいているようで、X(旧twitter)上での議論が盛り上がってきた。
有力AIベンチャーExa.aiのWill Bryk氏は「o1は(生成AI登場以来の)最大のAIの進化。非常に興奮している」と語っている。クラウドストレージのBox社のAron Levie氏は「AI論理的思考の飛躍的な進歩」、有名ポッドキャスターのLiron Shapira氏は「恐ろしく優秀」、著名エンジニアのMickey Wrigley氏は「思考力、計画力、実行力は桁外れ」とそれぞれ絶賛している。
こうした議論を眺めていると、o1シリーズの2つの特徴に注目が集まり始めているようだ。
1つは、o1シリーズでは論理的思考プロセスが強化され、ユーザーからのフィードバックを受けて、論理的思考が今後どんどん強化される可能性があるということだ。専門的に言うと、RLHF + CoTというぐるぐるモデルが回り始めるということだ。
例えばこれまでのAIに「底辺5cmで高さが2cmの三角形の面積は?」と聞くと、これまでのAIは、ネット上に「底辺5cm高さ2cmの面積は5平方cm」という記述があれば、「5平方cm」と答える。しかしまったく同じ記述がなければ、それらしい答えをもっともらしい表現で適当に返してくる。ハルシネーションと呼ばれるウソ回答だ。しかし「5」と答えればユーザーから「いいね」評価をもらえるので、同じ質問には「5」と答えるのがいいのだとAIは学習する。しかしなぜ答えが「5」になるのかは一向に学習できない仕組みだ。
ところが論理的思考が強化されたAIは、この質問に対していろいろな思考プロセスで答えようとする。中でも①公式を見つけてくる②公式に数字を当てはめる③計算する、という思考プロセスを得て出した答えに対して、ユーザーから「いいね」をもうらうと、この①②③の思考プロセスが正しかったと理解する。このように多くのユーザーとのやり取りを繰り返していくと、AIの論理的思考プロセスがどんどん複雑に洗練されていく。これまでのAIが「物知りのAI」だとすれば、o1シリーズからのAIは「地頭のいいAI」に進化していくことになるわけだ。
o1シリーズのもう一つの特徴は、学習プロセスだけでなく、推論プロセスででもスケール則が有効になるということだ。スケール則とは、計算資源の量と質、計算式の大きさ、学習データの大きさという3つの要素に、AIの性能が比例する、という経験則だ。一般的には高性能の半導体を数多く揃えればAIが進化する、というような意味合いで理解されていて、大手AI企業間での高性能半導体の買い占め競争や、大型データセンターの建設競争が繰り広げられている。
AIにおける半導体の用途としては、AIモデルをトレーニングする「学習」プロセスと、学習済みのAIモデルを実際に使って問題を解く「推論」のプロセスがある。これまでは「学習」に大量の半導体が割り当てられていた。一般的に学生は、テスト前に何時間も勉強するのに、テストを受けるのはわずか1時間程度。「推論」よりも「学習」に桁違いのエネルギーを注ぐわけだ。
同様にこれまでは「学習」に大量の半導体を使うことでAIが進化してきた。スケール則が有効だったわけだ。しかしそろそろスケール則も頭打ちになる、AIブームが幻滅期に入るという説が浮上してきた中で、「考えるAI」つまり「推論」プロセスが重要なAIのパラダイムが始まった。「学習」に加えて「推論」でもスケール則に従ってAIが進化する可能性が出てきたわけだ。
Sam Altman氏を始めOpenAIの経営幹部は、今回のo1シリーズをあまり持ち上げないようにと一生懸命だが、OpenAIの現場のエンジニアたちはそうした社の方針にはお構いなし。X上に好きな意見を投稿している。OpenAIエンジニアのWill Depue氏は「これが新しいパラダイムだということを人々に理解してもらいたい」と投稿している。また「これまでと同じペースで進化するわけがない。o1の進化は、OpenAI史上、過去最速になる。今年はワイルドな年になりそう」とも語っている。
Sam Altman氏は、小さな進化ごとに新しいモデルを次々とリリースしていく意向を明らかにしているし、OpenAI以外のAI大手も論理的思考に取り組んでいたので、Depue氏の言うようにこれから新しいモデルが次々とリリースされるようになるのかもしれない。
また論理的思考能力の向上で、これまでは自動化が困難だったビジネスのワークフローが一気に自動化されることになるかもしれない。Box社のCEO、Aaron Levie氏は「ほとんどの企業向けAIの用途は、なまの知性と精度に依存している。この新しいモデルにより、さらに多くの機会が拓くだろう」とXに投稿している。また著名エンジニアのMckay Wrigley氏も「一番すごいのが、これでエージェントを無数に作れること。これを使って作られる製品の波は、われわれがこれまでに見たことのないようなものになるだろう」と語っている。一般事業会社も、o1などの「考えるAI」のモデルを活用してDXを推進したり、新たなサービスを開発していくようになるのだろう。
AI企業にとっても、一般事業会社にとっても、新しいパラダイムが始まったようだ。

湯川鶴章
AI新聞編集長
AI新聞編集長。米カリフォルニア州立大学サンフランシスコ校経済学部卒業。サンフランシスコの地元紙記者を経て、時事通信社米国法人に入社。シリコンバレーの黎明期から米国のハイテク産業を中心に取材を続ける。通算20年間の米国生活を終え2000年5月に帰国。時事通信編集委員を経て2010年独立。2017年12月から現職。主な著書に『人工知能、ロボット、人の心。』(2015年)、『次世代マーケティングプラットフォーム』(2007年)、『ネットは新聞を殺すのか』(2003年)などがある。趣味はヨガと瞑想。妻が美人なのが自慢。