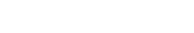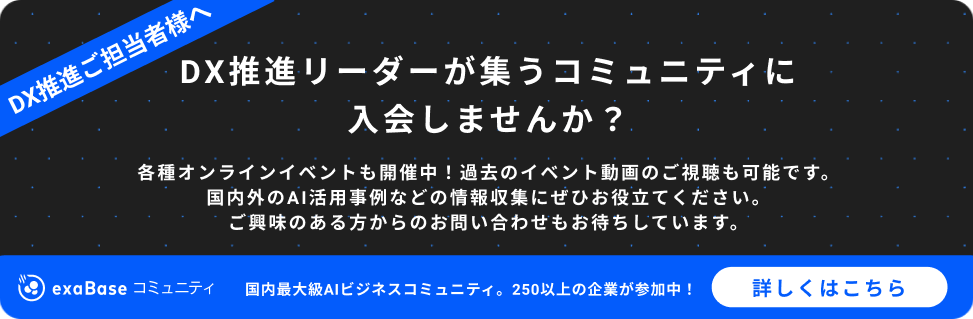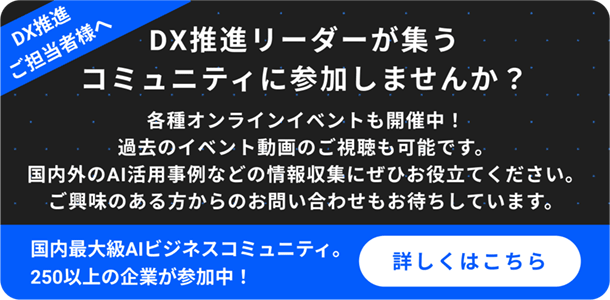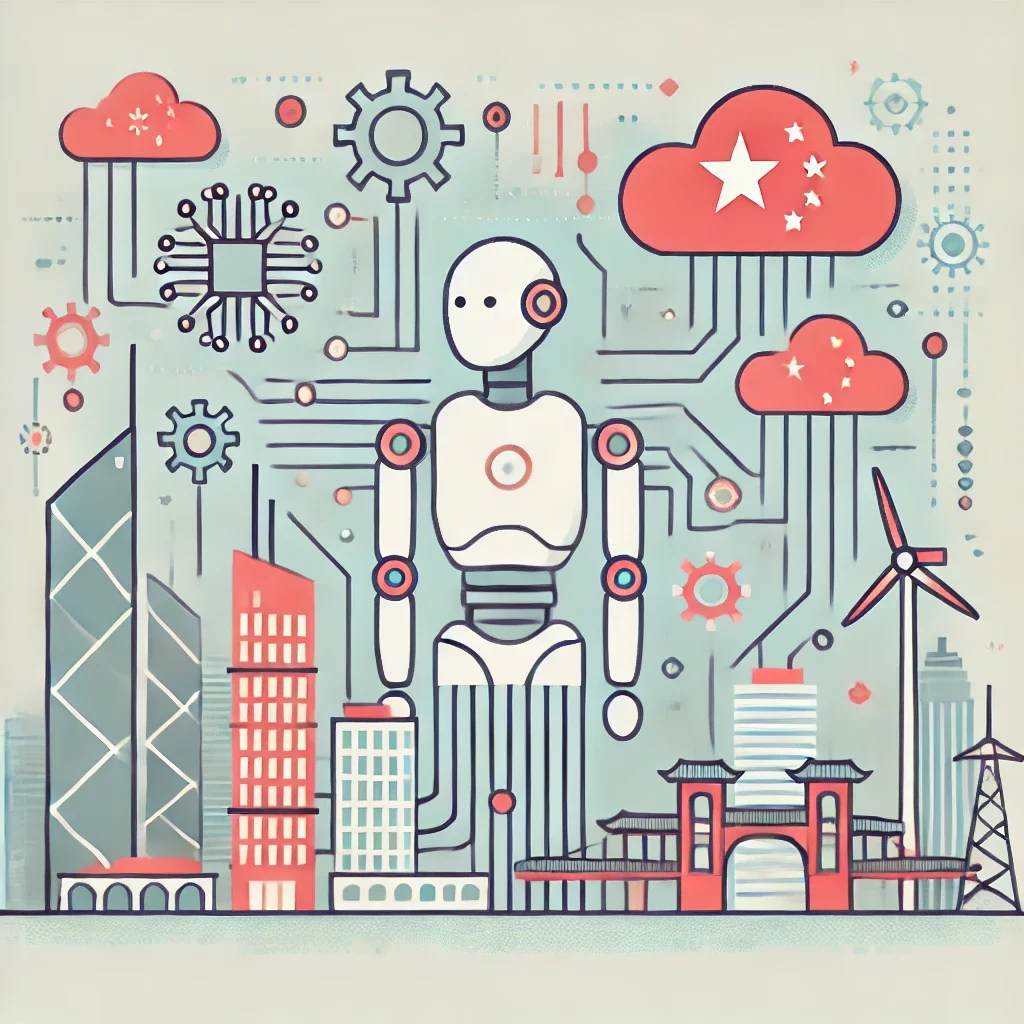
前回の記事を見て分かるように、OpenAIは明らかに中国AIの進化を脅威として捉えている。確かに中国製AIのDeepSeekのAIモデルは、米国製AIと肩を並べるほどの実力をつけてきた。しかし国家として利用を禁止しなければならないほどの脅威なのだろうか。利用を禁止することなどできるのだろうか。中国からのレポートをもとに、中国のAI業界の現状を探ってみた。
DeepSeekでAI化が急速に進む中国企業
DeepSeekを始めとする中国AIの急速な進化を受けて、中国の経済界が大盛り上がりだという話を耳にすることがあるが、果たして中国経済界は、どの程度AI化を進めているのだろうか。
中国のAI関連メディアの「大数据AI智能圈」が伝えたところによると、国有中央企業は驚異的なスピードでDeepSeekの採用を進めているという。
それによると2月初旬からわずか1か月足らずで、中央企業の45%がDeepSeekのAIモデルの導入を完了し、中央企業98社がDeepSeekサービスにアクセスできる状態になった。特定の技術の普及速度として「過去には想像できないようなスピード感」だとしている。
エネルギー業界では、中国石油天然気集団、中国石油化工集団、中国海洋石油集団の大手3社がDeepSeekのAIモデルの導入を完了している。
電力業界では、中国国家電網公司が電力網デジタル化プロジェクトの研究開発効率を大幅に向上させたし、中国南方電力網は電力ビッグモデルシステムをDeepSeekに完全に移行。中国華電はAIアシスタントをリリースしたという。
またDeepSeekは電力網設備の稼働データを学習し、ミリ秒レベルの故障診断の応答速度を実現。停電時間を大幅に短縮し、電力供給の安定性を確保することに成功した。中国国家電網公司は、DeepSeekを使用することで、リアルタイムの電力需要、発電状況、天候などの要因に基づいて電力リソースを正確に割り当てることに成功。エネルギーの無駄を減らし、電力網の運用効率を向上させている。
自動車製造業では、長安汽車のDeepBlue自動車システムがDeepSeekモデルに接続、東風グループは全LLMへのDeepSeekの接続が完了したという。
建設業界では、中国鉄道第一局がシステムAIアシスタントやプロセスAIアシスタントなどをDeepSeek R1で構築。
China Mobileは、カスタマーサービスにDeepSeekを活用。質問と回答の認識精度が90%を超えており、正確で明確な回答を提供し、ユーザーとの自然でスムーズな会話を実現している。
PetroChinaは貯留層開発や地震データ処理などの複雑なビジネスへのDeepSeekの応用を積極的に模索しているという。
「大数据AI智能圈」によると、DeepSeekと中央企業の協力は今後より深い統合の段階に入り、企業のDXは、初期応用から総合インテリジェンスへ、単一ポイントのシナリオ突破からフルチェーンのビジネス再構築へ、効率改善からイノベーション主導の開発へと移行するという。またこのプロセスを通じて、「中央企業の革新の活力と発展の潜在力を大幅に発揮させ、中国経済の質の高い発展を強力に推進するでしょう」と語っている。
Nvidiaの独占をも脅かすDeepSeek=AI大模型工场
同じくAI関連メディアの「AI大模型工场」によると、DeepSeekは2/28までに、モデルトレーニング、推論最適化、ハードウェア適応のチェーン全体を網羅するFlashMLA、DeepEP、DeepGEMMなどのコアモジュールをオープンソース化した。このことに関し華東師範大学の王偉教授は「DeepSeekはオープンソースで世界中の開発者を惹きつけており、NvidiaのCUDA独占を覆す可能性がある」と語っているという。
NvidiaのCUDAとは、同社の半導体に特化したソフトやツール群。Nvidiaが自社の半導体GPUの能力を最大限に引き出すために開発した技術だが、多くのサードパーティーの開発者や研究者がCUDAを利用した独自のライブラリ、ツール、およびアプリケーションを開発し、CUDAの普及と発展に貢献している。このエコシステムがNvidiaの最大の強みだと言われている。
今回DeepSeekがオープンソース化したFire-Flyerファイルシステムは、高速なデータアクセスが可能なSSDと、高速かつ効率的なネットワーク通信が可能なRDMA技術を組み合わせることで、AIモデルの学習や推論に必要な大量のデータを高速に処理できるという技術。この技術を核にNvidia以外の半導体に適応したソフトやツール群が世界中のエンジニアによって開発され、NvidiaのCUDAに対抗するような新たなオープンエコシステムが誕生する可能性がある。王偉教授は、そういう可能性を指摘しているわけだ。
資金力の勝負からオープンソースの知力の勝負へ
「AI大模型工场」によると、DeepSeekだけではなく、中国のIT大手が自社モデルを次々とオープンソース化して成功を収めているという。
アリババは推論モデルのQwQ-32Bをオープンソース化したほか、オープンソースの映像生成モデル「万向2.1(万)」を公開。同モデルはダウンロード数が100万回を超え、中国の映像生成モデルとして初めて、世界ランキングの1位に輝いた。
またバイドゥ(百度)は、3月16日にリリースした文心ビッグモデル4.5を、6月30日にオープンソース化する計画という。
AI大模型工场によると、DeepSeekが高いコストパフォーマンスとオープンソース戦略で、クローズドソースの巨大企業の技術的独占を打破。このことに背中を押された形で、バイドゥなどのクローズドソース企業がハイブリッド戦略へと方針を転換したという。
DeepSeekの成功の1つの要因はオープンソース戦略を取ったこと。AIを大手企業に独占させるのではなくオープンソースとして全人類で共有すべきだというオープンソースの考え方に賛同する世界中のエンジニアがDeepSeekのエコシステムに参加。月間ユーザーは1億人を超えたという。
AI大模型工场は、米国の主要AI企業の研究開発を資金力勝負の「資本集約型」と定義し、DeepSeekは「知的集約型」にシフトさせようとしていると指摘している。
AI大模型工场は「オープンソースによってもたらされる技術の普及は、AIを一部のエリートのための技術から社会インフラへと転換させ、最終的には産業全体がアプリケーションの爆発的な普及期を迎えることになる」と結んでいる。
中国オープンソース2大巨頭 DeepSeekとアリババ
一方で伝統的報道機関の新華社通信は、「春節前はDeepSeekがApp Storeで首位。春節後はアリババのTongyiシリーズが世界最大のオープンソースモデルになった」と報じている。
報道によると、アリババクラウドが3月6日に新しい論理的思考モデル「Tongyi Qianwen QwQ-32B」をリリースし、オープンソース化したところ、オープンソースコミュニティのサイトHugging Faceのトレンドリストでトップになった。Hugging Faceでは、世界中のエンジニアによって開発されたTongyiシリーズの派生モデルの数が10万を超え、2月のHugging Faceのオープンソース大型モデルリストのトップ10はすべて、アリババのTongyiシリーズモデルをベースに開発された派生モデルだったという。あっという間にアリババのTongyiは世界的なオープンソースモデルとなったわけだ。
AI技術はあらゆる業界に利用されることから、Alibaba Cloudに対する需要が急速に伸びているという。アリババグループの2025年度第3四半期財務報告によると、アリババクラウドの収益は前年比13%増の317億4,200万元で、AI関連製品の収益は6四半期連続で3桁の成長を維持しているという。
新華社通信は、「DeepSeekとアリババのオープンソース戦略は、中国のAI開発の方向性を変えた。AIが推進する技術競争、投資熱、産業の高度化も、中国の経済情勢を大きく変えることになるだろう」と結んでいる。
AIは中国で人型ロボットにも波及
AIに加えて中国が力を入れているのが人型ロボットだ。AIモデルはマルチモーダル化が進んでおり、言語データに加えて映像や音声データなども処理できるようになってきている。こうしたマルチモーダルAIが人型ロボットに搭載されることで、人型ロボットの性能の急速な向上が続いている。
AI大模型工场によると、ロボットメーカー優必選(UBTECH)の人型ロボット「Walker S1」はBYDやGeelyなどの自動車工場での実証実験が完了。効率が30%~100%向上したことから、第2四半期に自動車工場に大量納入される予定だという。
また宇樹科技(Yushu Technology)が、一般消費者向けの人型ロボット「G1」を9.9万元(約200万円)という低価格で予約販売を開始したところ、最初の注文分はすぐに完売。一般消費者向けにも、潜在的な可能性があることが明らかになったとしている。Yushu Technologyの人型ロボットは、自動車製造や電力設備の巡回点検といった危険な作業や反復作業の現場にも利用されているという。
AI大模型工场によると、AIモデルが音声や画像など多様な情報処理能力を統合することで、人型ロボットが複雑な環境により柔軟に適応できるようになってきているという。例えば、工場内で部品の組み立てや品質検査を行ったり、特定のシナリオ(感情的なやりとりなど)向けに最適化されたモデルにより、ロボットがより人間らしいサービス能力を持つようになってきているという。
中国はオープンソースコミュニティと一体化 排除は無理
中国からの情報を統合すると、AI産業を核にした中国の産業界の盛り上がりは相当のものだ。
またDeepSeekの成功に触発されて、中国の他のAI企業もオープンソース化することで大きく成長し始めた。さらに中国AI企業がオープンソースコミュニティの核になって、米国のクローズドモデルと対抗し始めた。
OpenAIが危機感を抱くのも無理のない話だ。あまりの危機感に、OpenAIは米国政府と同盟国での中国AIの使用禁止を提案してしまったのだろう。
ただ中国AIは世界のオープンソースコミュニティと一体化し始めた。たとえ中国AIを排除できたとしても、何万というその派生モデルをすべて排除することは到底無理だ。スタンフォード大学のAndrew Ng氏が言うように「もし米国がオープンソースを規制し続ければ、この分野での覇権は中国に移り、結果的に多くの企業が米国の価値観ではなく中国の価値観を反映したモデルを使用することになる」というだけの話だ。
もはやこの競争は、国家間の封じ込めや規制で決着するものではない。鍵となるのは、どちらがより多くの開発者やユーザーの信頼を集め、持続的なイノベーションの場を提供できるかということだ。AIの未来は、国境ではなく、コードとコミュニティの中にある。

湯川鶴章
AI新聞編集長
AI新聞編集長。米カリフォルニア州立大学サンフランシスコ校経済学部卒業。サンフランシスコの地元紙記者を経て、時事通信社米国法人に入社。シリコンバレーの黎明期から米国のハイテク産業を中心に取材を続ける。通算20年間の米国生活を終え2000年5月に帰国。時事通信編集委員を経て2010年独立。2017年12月から現職。主な著書に『人工知能、ロボット、人の心。』(2015年)、『次世代マーケティングプラットフォーム』(2007年)、『ネットは新聞を殺すのか』(2003年)などがある。趣味はヨガと瞑想。妻が美人なのが自慢。