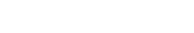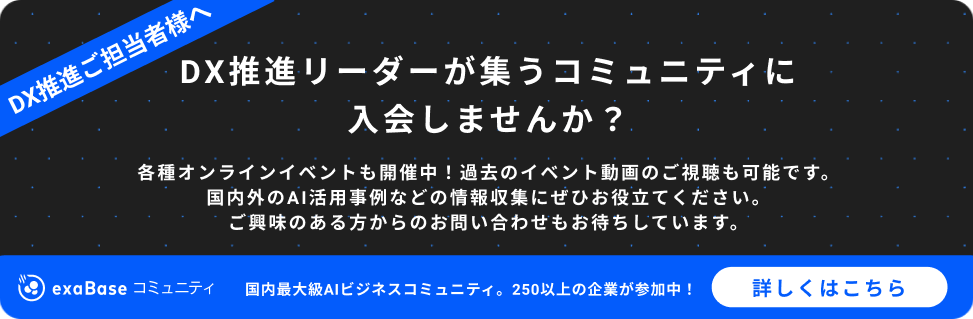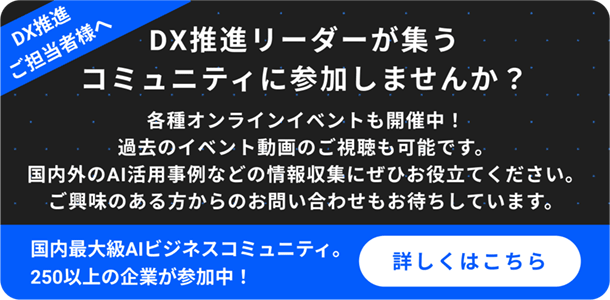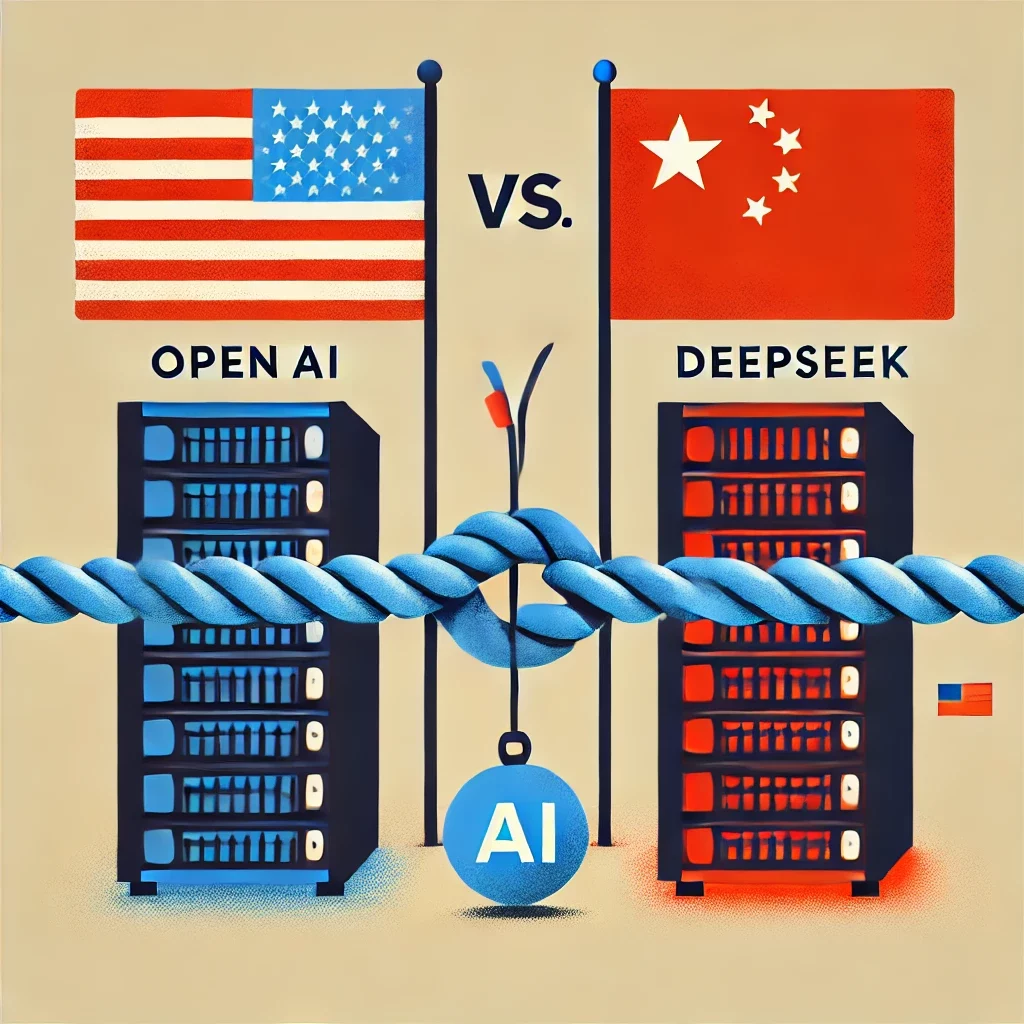
米有力IT情報サイトのTechCrunchによると、OpenAIは米国政府に提出する政策提案の文書の中で、米国政府と同盟国による中国DeepSeekの利用禁止を提案したという。DeepSeekのモデルをダウンロードし自国のサーバーにインストールする方法で利用することに関しては、非常に安全であることはAI業界関係者の間では常識。なぜOpenAIはこのような提案をしたのだろう。今回の原稿では、DeepSeekなどの中国AIの台頭に関する米国の関係者の意見をまとめて紹介し、次回の原稿では中国側の状況や見解を紹介したいと思う。
OpenAIが提出したのはトランプ政権の「AI行動計画」イニシアチブに対する提案文書で、TechCrunchの記事によると、DeepSeekはユーザーデータに関して政府当局の指示に従うよう法律で義務付けられているため、同社のAIモデル「R1」を利用することは危険だと主張。米国政府に対し、同社や中国が支援する同様の組織のモデルの利用を禁止することを検討するよう勧告しているという。また「ティア1」と呼ばれる最も信頼できる同盟国でも中国製モデルの使用を禁止すれば、知的財産窃盗のリスクを含むプライバシーとセキュリティリスクを防ぐことができるとしている。
かなりはっきりと利用禁止を求めているような内容だ。
提案文書を確認したところ、実際には「重要インフラやその他のハイリスクの用途でDeepSeekモデルを基盤として構築することには重大なリスクがある」「米国の外交政策は、中国に同調するAIインフラの世界的な禁止を求めていくべき」という表現になっている。TechCrunchの記事ほどはっきりとした表現にはなっていないものの、政府の力でDeepSeekの台頭を阻止してもらいたいという思いはありそうだ。
AnthropicやGoogleも提案書を出しているが、両社とも中国AIが米国AIに技術面で追い上げてきていることを認めながらも、中国AIを禁止すべきだという提案はしていない。
実際にDeepSeekは危険なのだろうか。
DeepSeekのアプリやウェブサイト、APIと呼ばれるソフトの接続口を通じてDeepSeekのAIモデルを利用すれば、ユーザーのデータはDeepSeek側に確かに渡る。しかしAIモデルをダウンロードして自国のサーバーにインストールして利用するのであれば、データは中国には送信されない。MicrosoftやPerplexity、Amazonなどといった有力企業は、米国や欧州に置いてある自社のサーバー上にDeepSeekのAIモデルをインストールしているので、それらのサービスを利用してもユーザーデータは中国に渡ることはない。
確かにDeepSeekのAIモデルの中に遠隔操作で侵入が可能なバックドアを仕込んでいる可能性がないとは言い切れない。しかしDeepSeekのモデルはオープンソースで公開されているので、誰でも自由に検証が可能。ここまで有名になったAIモデルにバックドアやバグなどがあることを見つけることができたエンジニアは、一瞬でヒーローになれる。高給の転職も思いのままになるだろう。というわけで今、世界中のエンジニアがバックドアを含むバグの検証に必死になっている。そう考えればDeepSeekほど安全なAIモデルはない、とも言えそうだ。
米国の他の識者や企業は、DeepSeekを危険だと捉えているのだろうか。
スタンフォード大学のAndrew Ng教授は、「DeepSeek-R1が公開されたことは非常に喜ばしい。技術レポートには多くの詳細が記載されており、透明性が高い」と絶賛している。DeepSeekの危険性を指摘する意見に関しては「潜在的な危険を誇張してオープンソースを規制しようとする動きがあるが、現在の流れは明らか。多くの企業が利用するようになるだろう」と語っている。さらには「もし米国がオープンソースを規制し続ければ、この分野での覇権は中国に移り、結果的に多くの企業が米国の価値観ではなく中国の価値観を反映したモデルを使用することになるだろう」と警告している。
実際に米国の大企業はDeepSeekを利用するための検証を始めているもようで、投資家のBrad Gerstner氏は「大企業の間でDeepSeekがAIモデルのナンバーワンの選択になっているという話を複数の半導体業界関係者から聞いた」とポッドキャストの中で語っている。
OpenAIのCEOのSam Altman氏は、DeepSeekのR1がリリースされた1月には「DeepSeek の R1 は、特に価格に見合った機能を提供している点において、素晴らしいモデルです。私たちはより優れたモデルを今後提供していきますが、新しい競合相手が出てくるのは本当に励みになります」と余裕の発言をX上に投稿している。
この余裕が、今回の米国政府への提案書には見られない。何があったのだろう。DeepSeekをはじめとした中国AIはどこまで進化してきているのだろう。(下)の原稿では、中国AI業界の現状と中国有識者の見解を紹介したい。

湯川鶴章
AI新聞編集長
AI新聞編集長。米カリフォルニア州立大学サンフランシスコ校経済学部卒業。サンフランシスコの地元紙記者を経て、時事通信社米国法人に入社。シリコンバレーの黎明期から米国のハイテク産業を中心に取材を続ける。通算20年間の米国生活を終え2000年5月に帰国。時事通信編集委員を経て2010年独立。2017年12月から現職。主な著書に『人工知能、ロボット、人の心。』(2015年)、『次世代マーケティングプラットフォーム』(2007年)、『ネットは新聞を殺すのか』(2003年)などがある。趣味はヨガと瞑想。妻が美人なのが自慢。