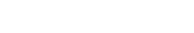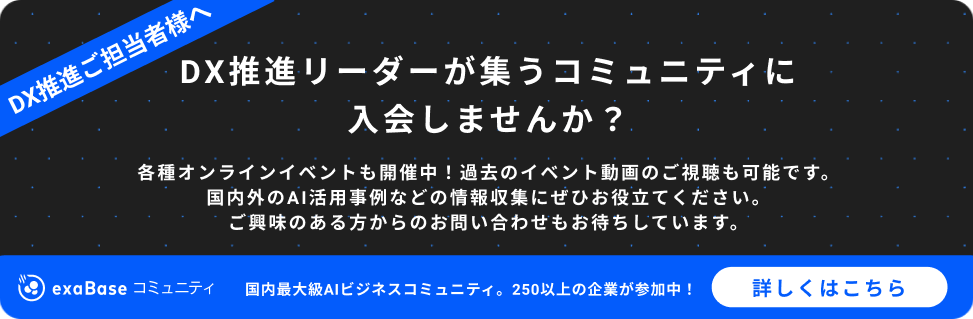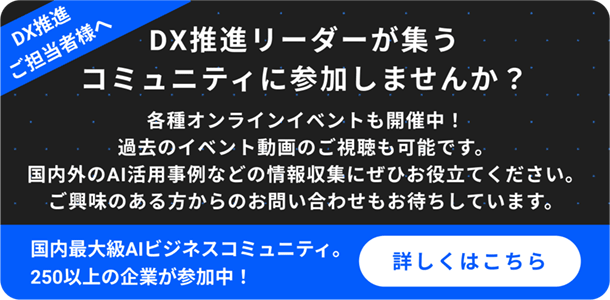秋口ぐらいからの仮想通貨の高騰を受けてか、仮想通貨が注目されるようになってきた。
僕自身、2年ほど前に自分が主催する勉強会「湯川塾」で仮想通貨を特集したことがある。その仕組みは本当によくできていて、そのときは「考えた人、天才!」と思った。ただそれでも僕自身は、仮想通貨にはそれほど興味を持てなかった。
興味を持っている人って、大別すると2つのタイプに分かれると思う。①仮想通貨が既存の金融や国家の枠組みを変えてしまうかもしれない、と思っている人。②投機として興味がある。この2つのタイプ。
僕自身、投機やギャンブル、さらに言えば金儲けにも興味がそれほどない。なので①の意味で少し興味を持ったが、特にいろいろ調べてみたいという気にはなれなかった。というのは仮想通貨が本当に既存の金融の仕組みを代替するような存在になるのかどうか、そのときはよくわからなかったからだ。
実は2年たった今でも、よく分からない。確かに可能性はなくはない。でも仮想通貨がそれだけで社会を大きく変えることのできるテクノロジーかどうかは分からない。なぜなら金融の世界って、政治の世界に非常に近い存在だからだ。
昨年暮れに湯川塾の別の期に講師として呼んだ外資系金融機関の関係者も同じようなことを言っていた。「仮想通貨がメジャーな存在になり金融業界を破壊的な状況に追いやることなんてありえないですよ。アメリカの金融業界は政府に非常に近い存在です。今は、痛くも痒くもないので仮想通貨を泳がせているだけ。仮想通貨がわれわれを脅かすような存在になったら、その時点で政治力をもってひねりつぶしますよ」。
アメリカの権力構造って本当はどうなっているのかは知らないけれど、彼のその発言には妙に説得力があった。
仮想通貨の草の根のパワーと、アメリカの金融機関。どっちが強いんだろうか。見守りたいと思う。

湯川鶴章
AI新聞編集長
AI新聞編集長。米カリフォルニア州立大学サンフランシスコ校経済学部卒業。サンフランシスコの地元紙記者を経て、時事通信社米国法人に入社。シリコンバレーの黎明期から米国のハイテク産業を中心に取材を続ける。通算20年間の米国生活を終え2000年5月に帰国。時事通信編集委員を経て2010年独立。2017年12月から現職。主な著書に『人工知能、ロボット、人の心。』(2015年)、『次世代マーケティングプラットフォーム』(2007年)、『ネットは新聞を殺すのか』(2003年)などがある。趣味はヨガと瞑想。妻が美人なのが自慢。